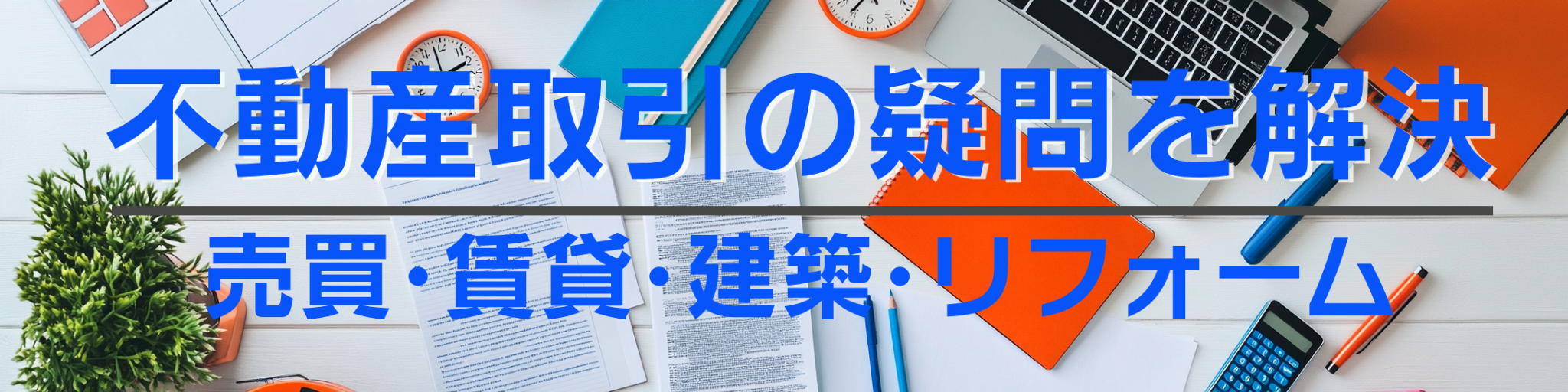建築現場で耳にする「尺」っていったい何?

不動産の質問
先生、不動産のチラシを見ていると、『尺』って書いてあることがあるんですけど、これって何ですか?

不動産の専門家
いいところに気がついたね。『尺』は、昔の長さの単位で、約30.3cmのことだよ。今はメートル法を使っているけど、昔からの習慣で、特に建築の分野では今でも使われているんだ。

不動産の質問
へえー、そうなんですね。じゃあ、チラシに『6尺』って書いてあったら、180cmぐらいの部屋ってことですか?

不動産の専門家
その通り! 正確には181.8cmだね。このように、不動産の世界では昔の単位が使われていることがあるから、覚えておくと便利だよ。
尺とは。
「尺」は、昔の長さの単位の名前で、一尺は約30.3cmです。尺よりも短い単位を「寸」、6尺の長さを「間」と言い、1平方間を1坪(約3.3平方メートル)と言います。1959年に「尺」を使った長さの測り方は廃止され、今ではメートル法が使われていますが、建物を作る仕事では、今でも尺や寸が使われることがあります。
身近な不動産用語「尺」

– 身近な不動産用語「尺」住宅情報誌やインターネットで物件情報を見ていると、「リビングダイニングは12尺」や「天井高は2尺4寸」といった表記を目にすることがあります。普段、私たちが使い慣れているメートル法とは異なる単位に戸惑う方もいるのではないでしょうか。この「尺」や「寸」といった単位は、かつて日本で広く使われていた尺貫法という長さの単位です。
今ではメートル法が主流となっていますが、日本の伝統的な建築物や、現代の住宅建築においても尺貫法は深く根付いています。そのため、不動産情報を読み解く上でも、尺貫法について理解しておくことは大切です。
尺貫法は、人の体の寸法を基準に作られた単位と言われています。「尺」は親指と人差し指を広げた時の長さをもとに定められており、約30.3cmに相当します。さらに「尺」は10等分されて「寸」となり、約3.03cmとなります。つまり、「12尺」のリビングダイニングであれば、約3.6m、「2尺4寸」の天井高であれば、約2.4m×3.03cm=約72.7cmとなります。
メートル法に換算することもできますが、尺貫法で表記されている場合は、日本家屋特有の空間の広がりや、部屋の雰囲気を感じ取ることができるという側面もあります。例えば、「6畳」と「12畳」の部屋では、広さが2倍であることは容易に想像できますが、「5.25畳」や「8.5畳」といった半端な広さの部屋をイメージするのは難しいのではないでしょうか。尺貫法では、畳のサイズを基準に部屋の広さを表すことが多く、部屋の構成や用途を具体的にイメージしやすいという利点があります。
日本の建築文化を理解する上でも重要な尺貫法。 next homeでは、お客様に寄り添い、快適な住空間探しをサポートいたします。
| 単位 | 説明 | メートル法換算 |
|---|---|---|
| 尺 | 親指と人差し指を広げた時の長さをもとにした単位 | 約30.3cm |
| 寸 | 尺の10分の1 | 約3.03cm |
尺貫法とは

– 尺貫法とは尺貫法は、メートル法が導入される1959年まで、日本で長く使われてきた長さ、面積、体積などを表す単位系です。馴染み深い畳のサイズや家の間取りなど、日本の伝統的な建築や文化に深く根付いています。
尺貫法の基本となる単位は「尺」で、約30.3cmの長さを表します。身近なもので例えると、大人の手のひらを広げた時の親指の先から小指の先までの長さが、だいたい1尺に相当します。尺よりも小さい単位には「寸」があり、1尺は10寸に相当します。つまり、1寸は約3.03cmで、これはちょうど大人の親指の幅くらいです。
反対に、尺よりも大きな単位には「間」があります。6尺、つまり約181.8cmが1間となります。 間は、主に部屋のサイズや建物の柱と柱の間隔などを表す際に使われます。 例えば、畳のサイズは1間×半間(約90.9cm)が基本とされており、日本の住宅の多くは、この畳のサイズを基準に設計されてきました。
このように、尺貫法は、人間の身体を基準とした単位系であるため、感覚的に理解しやすく、日本の風土や文化に根ざした単位系と言えるでしょう。
| 単位 | 長さ | 説明 |
|---|---|---|
| 1寸 | 約3.03cm | 大人の親指の幅くらい |
| 1尺 | 約30.3cm | 大人の手のひらを広げた時の親指の先から小指の先までの長さ |
| 1間 | 約181.8cm (6尺) | 部屋のサイズや建物の柱と柱の間隔 |
尺と坪の関係

不動産の広告を見ると、「坪」という単位をよく目にします。この「坪」は、現在では使われていない尺貫法と深い関わりがあります。
1坪は、1間の正方形の面積のことを指します。1間は約1.82メートルなので、計算すると1坪は約3.3平方メートルになります。
畳の大きさを例に考えてみましょう。畳1枚のサイズは、約1間×0.5間です。つまり、畳2枚分の広さが1坪に相当します。
尺貫法は、メートル法の普及に伴い、1966年に全面的に廃止されました。しかしながら、「坪」という単位は、現在でも不動産の取引において重要な役割を果たしており、土地や建物の広さを表す単位として広く使われています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1坪 | 約3.3平方メートル |
| 1間 | 約1.82メートル |
| 畳2枚分 | 1坪 |
建築現場における尺の重要性

日本では、建物の長さや高さなどを表す際にメートル法が広く使われていますが、建築現場では、今もなお「尺」や「寸」といった尺貫法が使われています。
尺貫法は、日本の伝統的な建築様式と深く結びついています。古くから木造建築が盛んだった日本では、柱や梁などの部材の寸法や、部屋の広さを決める際に、尺貫法が用いられてきました。そのため、古い設計図面や建築基準法など、建築に関する様々な資料や規格が尺貫法に基づいて作成されています。現場で働く職人たちは、これらの資料や規格に基づいて作業を行うため、尺貫法の理解が不可欠となるのです。
また、尺貫法は、現場での作業効率や正確性を高める上でも役立ちます。例えば、柱や梁などの木材は、尺貫法に基づいた寸法で流通していることが多く、メートル法に換算するよりも、尺貫法を用いる方がスムーズに材料を調達し、加工することができます。また、熟練の職人たちは長年の経験から、尺貫法の単位を用いて長さや空間を感覚的に把握することに長けています。そのため、現場では、メートル法よりも尺貫法を用いる方が、より直感的かつ正確に作業を進めることができると言われています。
このように、尺貫法は、日本の建築文化と現場での作業効率に深く根付いた、重要な単位系と言えるでしょう。
| 尺貫法のメリット | 解説 |
|---|---|
| 日本の伝統建築との関連性 | – 古くから木造建築で尺貫法が使用されてきたため、古い設計図や建築基準法などの資料は尺貫法に基づいている。 |
| 現場での作業効率と正確性 | – 木材などの建築資材が尺貫法に基づいた寸法で流通しているため、調達や加工がスムーズ。 – 熟練職人は尺貫法を用いた空間把握に長けており、直感的で正確な作業が可能。 |
まとめ

かつて日本で広く使われていた尺貫法は、メートル法の導入によって公式には使われなくなりました。しかし、日本の建築業界では、今もなお尺貫法が重要な役割を担っています。特に、長い歴史を持つ伝統的な建築様式や、古くから使われている建材との関わりが深く、現場での作業を効率的かつ正確に行う上で、尺貫法は欠かせないものとなっています。
例えば、畳の寸法は、今でも尺貫法を用いて表されることが一般的です。一畳の大きさは、約三尺×六尺とされ、この寸法は、日本の住宅設計の基本となっています。また、柱や梁などの構造材の寸法も、伝統的な建築物では尺貫法に基づいて決められています。
このように、日本の建築業界では、メートル法と尺貫法が併用されている場面が多く見られます。不動産情報や建築現場で、「尺」や「寸」といった単位を見かけた際には、日本の建築文化と歴史を感じながら、その意味を理解するように心がけましょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 尺貫法の現状 | 公式にはメートル法に移行したが、建築業界では今も重要。特に伝統建築や古い建材との関係が深い。 |
| 尺貫法の使用例 | 畳の寸法(一畳は約三尺×六尺)、柱や梁などの構造材の寸法。 |
| まとめ | 日本の建築業界ではメートル法と尺貫法が併用されている。 |