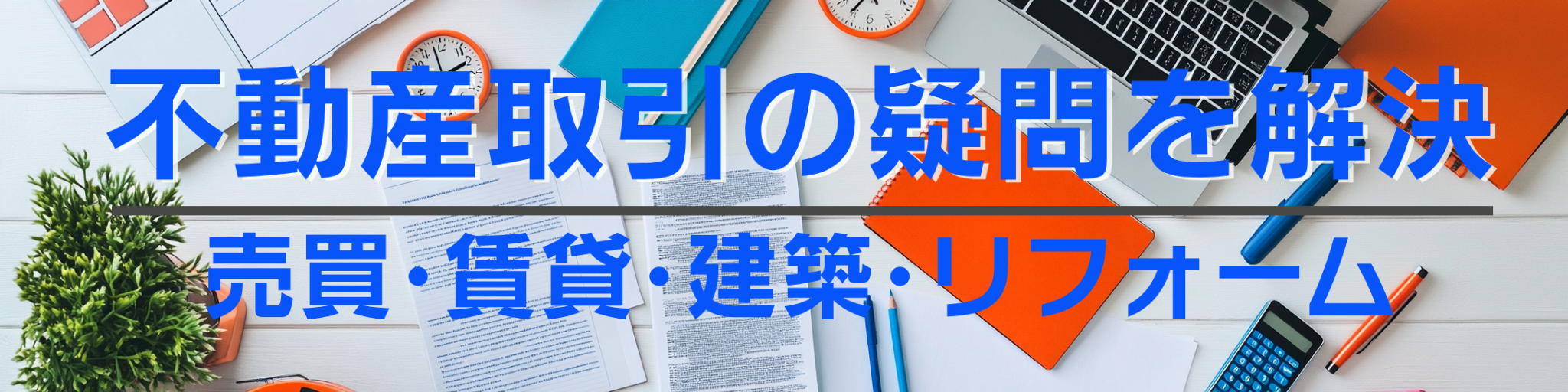その他
その他 震度
 その他
その他
日々ニュースなどで地震の情報を目にしますが、その大きさを表す単位には複数あり、それぞれが異なる側面を持っています。
まず、ニュースで頻繁に耳にする「震度」は、ある地点における揺れの強さを表す尺度です。震度は体感や周囲の状況から計測され、同じ地震であっても場所によって異なります。一方、「マグニチュード」は地震そのものの規模、つまり地震によって放出されたエネルギーの大きさを表します。マグニチュードは世界共通の指標であり、地震が発生した場所に関わらず一つの地震に一つの数値が付けられます。
その他に、「ガル」という単位も地震の大きさを表す際に用いられます。ガルは地震計で計測される地面の揺れの加速度を表しており、揺れの強さをより定量的に示すことができます。また、「カイン」は地震のエネルギーの大きさを表す単位であり、マグニチュードと同様に地震の規模を示す指標となります。
このように、地震の大きさを表す単位にはそれぞれ異なる意味と役割があります。これらの単位の特徴を理解することで、地震の情報をより深く理解することができます。
Read More
 その他
その他 過去の地震の大きさを知る「激震」とは?
地震が多い日本では、地震の揺れの強さを示すために「震度」という尺度がよく使われています。かつて、気象庁は最も激しい地震の揺れを表現する際に「激震」という言葉を使っていました。「激震」は、建物の3割以上が倒壊してしまうほどの凄まじい揺れのことです。激震に見舞われると、山が崩れ落ちたり、地面が大きく裂けたり、断層が現れたりと、私たちの生活にとって深刻な被害が発生します。
「激震」は、1949年から1960年までの期間、気象庁によって震度7を表す言葉として使用されていました。当時の震度は、体感や被害状況に基づいて、0から7までの8段階で評価されていました。しかし、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに、震度階級はより客観的な基準で評価される必要性が浮上しました。
そこで、1996年10月からは震度5と震度6がそれぞれ弱と強に分けられ、従来の「激震」は「震度7」と表現されるようになりました。震度7は、計測震度計を用いて計測した値に基づいて決定され、これまでの体感や被害状況による評価よりも、より正確で客観的なものとなっています。この変更により、地震の規模や被害状況をより的確に把握できるようになり、防災対策の強化にも役立っています。
Read More